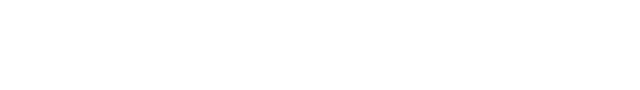咽頭の病気
口腔・咽頭の構造
写真1:正常な口腔、咽頭の構造
- 口腔:歯、舌(①)、唾液腺、硬口蓋(こうこうがい)などがあります。
- 咽頭:上・中・下咽頭に分けられ、口蓋扁桃(②)、軟口蓋(なんこうがい)(③) などがあります(写真1)。
口腔・咽頭の働き
口腔・咽頭の機能には、味覚、そしゃく機能、嚥下機能があります。
- 味覚:舌の後方にある味蕾(みらい:味覚の受容器)で各種の味を感じます。
- そしゃく機能:食物を細かく噛み砕くことをいいます。
- 嚥下機能:噛み砕かれた食物を唾液で飲み込みやすいようにして、下咽頭まで送ります。
急性扁桃炎
写真2:矢印は膿栓を示します
- 症状:咽頭痛、発熱、頸部リンパ節腫脹など。
- 原因:小児や青年期に多く、気候の変動、風邪などから口蓋扁桃に細菌感染したものをいいます。
- 治療:発熱時は安静にし、抗菌剤の内服や点滴などの治療を行います。 感染初期は扁桃が赤く腫れあがり、続いて膿栓ができます。(写真2)
扁桃周囲炎・膿瘍
-
写真3:膿瘍ができ軟口蓋が
著しく腫脹している (矢印)。症状:咽頭の激痛、発熱、嚥下障害など。
- 原因:20~30歳代に多く、急性扁桃炎に引き続いて発症し、炎症が周囲にひろがったものを扁桃周囲炎、さらに膿瘍ができたものを扁桃周囲膿瘍(写真3)といいます。
- 治療:抗菌剤、鎮痛剤などの内服投与や点滴治療を行います。扁桃周囲膿瘍の場合には針や切開による膿の除去も行います。
伝染性単核症
-
写真4:膿栓が多数、
付着しています(矢印)症状:咽頭痛、発熱、全身倦怠感など。
- 原因:EBウイルスが口蓋扁桃、咽頭扁桃などに感染し、頸部リンパ節腫脹や肝脾腫を引き起こします(写真4)。
- 診断:急性扁桃炎に比べ発熱が軽度で、発症からの経過が長い場合は、伝染性単核症が疑われます。EBウイルス抗体価の上昇などで診断します。
- 治療:安静、対症療法でほとんど治りますが、鎮痛解熱剤やステロイド剤を投与することもあります。
喉頭の病気
喉頭の構造
写真1:正常な喉頭(矢印:声帯)
喉頭は、下咽頭と気管の間にある宙吊りの組織で、軟骨などの支持組織と声帯などからなっています(写真1)。
喉頭の働き
喉頭の機能には、呼吸機能、発声機能、下気道の保護があります。
- 呼吸機能:吸気時には声帯が広がり、呼気時には狭くなり、肺から空気を流出させないようにします。
- 発声機能:声帯を閉じて、声帯の振動で発声することができます。
- 下気道の保護:嚥下の時、喉頭腔を咽頭から閉鎖し、食物が気管に間違って入ってしまうのを防ぎます。
急性喉頭炎
- 症状:嗄声(声がれ)、喉頭の違和感、嚥下痛など。
- 原因:病原ウイルスなどに感染し発症します。
- 治療:軽症の場合、声の安静が必要であり、抗生剤などの吸入を行います。喉頭浮腫(炎症による腫れ)のため呼吸困難を伴う場合には、入院治療が必要となります(写真2)。
- 写真2:重症例:喉頭浮腫を伴います
- 写真2:重症例:喉頭浮腫を伴います
クループ症候群
-
写真3:声帯下の粘膜が腫脹しています(矢印)
症状:乾燥性の嗄声(声がれ)、咳発作、発熱など。
- 原因:冬期、5歳以下の小児に多く発症します。両側の声帯下粘膜が腫れ、気道が狭くなるため、呼吸が苦しくなります(写真3)。
- 治療:抗生剤等の投与を行います。重症の場合には、副腎皮質ホルモン剤の投与を行います。
- 予後:一般には治療後は良好ですが、呼吸困難を伴う場合には、入院が必要になります。
喉頭ポリープ
-
写真4:左声帯が全体的に腫れている(矢印)
症状:嗄声(声がれ)、喉頭の違和感など。
- 原因:声の酷使(使いすぎること)、喫煙、感染などが引き金になり発症します。
- 治療:一般に、沈黙療法やステロイド吸入などの保存的治療により治ります。6ヶ月以上経っても改善しない場合には、ポリープ切除術が必要です。小さなポリープであれば日帰り手術が可能ですが、重症例では入院下での手術が必要です(写真4)。